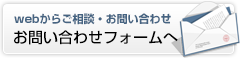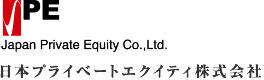コラム “志・継・夢・承”
|
2024年 |
-
2024年12月 Vol.63“2024年+2025年~”問題
-
2024年11月 Vol.62灯火親しむべし
-
2024年10月 Vol.61突き動かされる
-
2024年8月 Vol.60M&Aの「ない」「のに」「ちがう」
-
2024年6月 Vol.59“鳥の眼”と“魚の眼”
-
2024年4月 Vol.58『退職年表』と『社員ピラミッド』
-
2024年1月 Vol.57今を生きる
“2024年+2025年~”問題Vol.63 |
|
地球温暖化のせいか、単なる年齢のせいか、年々、季節感が薄れています。が、はや1年を振り返る時期です。 今年4月には、“2024年問題”として懸念されていた、運送業・建設業・医師の時間外労働時間の上限規制が始まりました。“働き方改革”という名の下での現場の我慢や努力、経営の工夫は、今なお続いています。そのなかで、人件費をはじめとした諸々のコスト上昇に耐えきれずに事業継続を断念して廃業や解散を選択する、あるいは倒産した企業も増えています。これは2024年だけの問題ではなく、2025年以降もじわじわと影響を及ぼし続けるゆえ、“2024年~(から)問題”という方が適切かもしれません。 そして、来年の“2025年問題”は、超高齢化社会の到来です。 1947年から1949年に生まれた“団塊の世代”の方がすべて75歳を迎え、75歳以上の後期高齢者が2024年1月の約2,020万人から2,155万人へと大幅に増えて全人口の5人に1人(約18%)となります。さらに、前期高齢者となる65~74歳の1,498万人を加えると凡そ3,650万人と、3人に1人が高齢者です。社会保障費の負担や医療・介護サービスの維持、労働力確保等、社会全体に深刻な問題が生じると懸念される数字です。 そして、“2025年問題”はさまざまな業界に派生します。例えば、不動産業界では、空き家の増加や不動産価格の下落、IT・情報分野では“2025年の崖”を前に老朽化・複雑化したシステムの維持構築のための人員不足などが懸念されます。こちらも2025年に限った問題ではなく、“2025年~(から)問題”になるといえます。 “2024年問題”が2025年以降も続くなかで“2025年から問題”が始まる。再来年には、当然、“2026年問題”も控えています。ちなみに、2026年には、AIの学習に必要なインターネット上の良質な大量のデータが枯渇すると予測されています。結局、毎年、問題は起き、日本社会が抱える課題は重層的に積み上がっていくようです。 もう、ここまでくれば、『毎年なにか起きるのは当たり前!』と覚悟を決めて、常に先を読んで変化対応するしかありません。環境の変化に応じて、社会が変わる、会社も変わる、経営者自身も変わる、働く人の意識も変わる、そして、変えていく。 環境の変化は見通せなくとも、とりあえず、会社もしくは自分自身の“2025年~問題”を見通したうえで新しい年を迎えるのがよさそうです。 以 上 |
| <真> 2024年12月 |
灯火親しむべしVol.62 |
|
秋の夜長、お手元の本はどこで手に入れたものですか?駅前の本屋?ネット書店?古本チェーン店?地元の図書館?いや、そもそも読んでいるのは電子書籍でしょうか。 書店が倒産や休廃業で減り続けています。2023年度の書店の総店舗数は全国で10,918店と10年前の15,602店の7割ほど、1年間の閉店数は614、新規開店は92(出版科学研究所調べ)と減少に歯止めがかかりません。 また、“書店のない市区町村”が24年8月末時点で全国の27.9%(出版文化産業振興財団調べ)という数字もあり、経済産業省は、“地域の文化拠点”である書店がなくなることに危機感を抱き、「書店振興プロジェクトチーム」を立ち上げ、『書店経営者向け支援施策活用ガイド』を作成して、小さな書店の売上拡大や業務効率改善の助言や事業承継、M&Aについて解説、啓蒙しています。 ただ、書店業界は、他の業界のように、大企業や同業によるM&Aで業界再編が進んでいるわけではありません。「インターネットやコンビニなどへの販売ルートの変化」や「紙媒体からデジタルへの移行」、「圧倒的な品揃えで大型化するリアル店舗」、「ライフタイル提案型店舗への業態転換」など、業界そのものが変容しています。 こうした背景には、いわゆる“再販制度”で定価販売に守られてきたことで競争原理や規模の経済が働かず、M&Aによる規模拡大や新規参入のメリットがないという、書店業界特有の事情があります。 本ではなくスマホ片手に出かけてマンガを読み、雑誌はコンビニや駅の売店で買えばいいという時代、もはや、雑誌に依存した薄利多売のビジネスモデルでは書店経営は成り立ちません。先の「書店振興プロジェクトチーム」が10月にまとめた『全国書店ヒアリングでの声』には、小さくともリアルであることの魅力をもつ“個性的な本屋さん”として生き残るだめの示唆がたくさんあります。 本に囲まれた空間で紙やインクの匂いに包まれて、知らない本と出会い、好奇心や知識欲が満たされる喜びや心地よさも改めて伝えたいものです。 灯火親しむべし。そのために、本屋さんを残す方法、灯火考えるべし。 以 上 |
| <真> 2024年11月 |
突き動かされるVol.61 |
|
『はがき63円→85円』 『封書84円→110円』 10月、郵便料金が約3割値上げとなりました。これまでも消費税増税に伴って小刻みな価格改定はあったものの、郵便料金そのものの値上げは1994年以来、なんと約30年ぶりとのことです。 そして、最低賃金も上がります。コロナ明けの2022年以降、全国の加重平均での引き上げ幅は30~40円と拡大していましたが、今回は過去最大51円の引き上げ、時給ベースで1,055円となり、デフレからインフレへという流れをひしひしと感じます。 日本の新しいリーダーは、『最低賃金を2020年代のうちに全国平均1,500円にする』と目標を掲げました。今後5年で毎年90円ほどの引き上げが本当に実現するかどうかは別にしても、デフレに慣れた人はみな物価高を前にして給料が増えることを期待し、一方の企業側は、最低賃金法という法律を前提に今後の経営を考えなくてはなりません。 特に、中小企業経営者は、最低賃金の“引き上げ”に“突き上げ”られながらの経営が迫られます。例えば、人材獲得競争に勝つために賃金を引き上げる、社内の賃金テーブルのバランスが年齢や年代で崩れないように給与体系を見直す、そのために評価制度を構築する、さらに社会保険の負担増を踏まえて採用形態や働き方を変える・・・など、最低賃金の引き上げは、単に、給与額だけの話ではなく、会社の経営そのものに変容を促すべく、経営者を突き動かします。 5年後、最低賃金が本当に今の1.5倍になったら、その時、2030年に笑顔で経営をしているか?笑顔で引退しているか?“その時”までに、いや、“その前”に、今、一歩踏み出して行動しろと突き上げられ、突き動かされる、いよいよ、“その時”が来たようです。 以 上 |
| <真> 2024年10月 |
M&Aの「ない」「のに」「ちがう」Vol.60 |
|
世の中に“M&A”が当たり前のように広がってくると、当たり前のように悪事を働く人も出てきます。これは、M&Aが1つの“産業”として定着してきたからともいえます。しかし、中小企業の事業承継に関わるM&A、つまり、“自分の会社を売る”というM&Aに二度はなく、売ったら終わり、取り返しがつきません。期待外れの高級レストランで『金返せ!』『もう二度と行かない!』とつぶやいて済むような話ではなく、売った会社(株式)はもちろん、支払った手数料も戻ってこない、さらには、自分や家族、社員の人生も巻き込んで、重い荷物を抱えてしまうこともあるでしょう。これは、売り手だけでなく、買い手としてもありうることです。 M&Aを支援する機関として中小企業庁に登録している法人・個人は直近で大小2,300者超、もちろん、他にもM&Aをビジネスにしている人は数多いますし、今も日本のどこかで、毎日数件のM&Aが成立しているわけですから、M&Aに関するクレームやトラブルが目についてくるのも当然です。例えば、その不平不満の声は、『ない』『のに』『ちがう』という3つのワードに集約できたりします。
こうした『ない』『のに』『ちがう』の原因は同じだったり、複合的な要因で生じたりもします。ただ、その原因が、明らかに騙す意図のある“詐欺”なのか、アドバイザーのプロフェッショナルとしての力量不足ゆえに起きる“トラブル”なのか、はまったく別の話です。中小企業のオーナー経営者が、M&Aに関しては、知識・情報・経験という点で弱者であるのは致し方ないとはいえ、『ない』『のに』『ちがう』を回避するための見極めと対応は、経営者として絶対に必要なものとなりました。 もはや、M&Aは、買いでも売りでも、経営者にとって特別なことではなく、経営課題の一つであり、経営者としての大事な仕事の一つになったと考えて、向き合っていかなくてはなりません。 以 上 |
| <真> 2024年8月 |
“鳥の眼”と“魚の眼”Vol.59 |
|
新入社員の頃、職域営業の勧誘やお付き合いで加入した生命保険が30年以上の時を経て、契約の更新や満了を迎える年齢になりました。ひさしぶりに訪れた生命保険会社の営業所では、壁に貼られたスローガンや個人成績グラフといった光景は昔と変わらぬままでしたが、生保レディの手元にはタブレット、個人情報や契約内容が一目瞭然でシミュレーションもその場で自由自在、電子署名ゆえ印鑑不要と、現場のデジタル化がしっかり進んでいて驚きでした。こうして何十年という単位で息の長いビジネスをしてきた生命保険会社が、本業への危機感と次の時代を見据え、数千億円という資金を投じて“時間”を買い始めました。 日本生命は、昨年11月、介護最大手のニチイ学館を約2,100億円で買収、介護・保育・医療事務という事業を手中に収めました。超高齢社会において、サービス提供体制の高度化を図るため、本業の保険販売にすぐには結びつかなくとも、生命保険を中心にさまざまな安心を届ける“安心の多面体”を目指すものです。 また、第一生命は、1万5,000社を超える企業や団体に福利厚生代行サービスを提供するベネフィット・ワンを約2,920億円でTOB(株式公開買い付け)、今後、完全子会社化して、従来の“保険業”から“保険サービス業”へという事業変革の中核に据えます。約950万人の顧客を有する福利厚生サービス事業のプラットフォームは、健康・医療やつながり・絆といった体験価値領域の事業の拡大を目指すなかで保険事業との相乗効果が期待されるものとなります。 明治安田生命保険は、業法上、“生命保険”という文字が社名から外せないゆえ、ブランド通称を『明治安田』に変更、保険だけを扱うイメージから脱却し、生命保険会社の役割をも超えた、予防医療や健康増進、さらには格差や孤立などの社会課題を解決する企業でありたいとしています。 生保業界に限らず、こうして、業界を超えて、
が、大企業・中小企業を問わず、すべての業界、すべての企業に求められるようになった・・・と、昔ながらの生命保険会社の営業所での待ちあい時間、時の経過と時代の変化に思いを巡らせていました。 以 上 |
| <真> 2024年6月 |
『退職年表』と『社員ピラミッド』Vol.58 |
|
今年の春は、少し遅い桜が入社式や歓迎会と重なって、少し華やかに季節が始まりました。 上場企業となれば「社員の平均年齢」が公表されていますが、自分の会社も含め、意外と知らなかったりします。例えば、「トヨタ自動車40.6歳」、「ソフトバンクグループ40.5歳」、「ファーストリテイリング38.0歳」、「楽天グループ34.4歳」など、企業イメージとは違った、意外な数字が並びます。ちなみに、昨年上場したアパレル企業のyutoriの社員の平均年齢は27.1歳、片石社長は30歳です。 社員の平均年齢は、会社の姿を映し出す1つの数字です。その数字には、いろいろな背景が隠れていて、そもそも新入社員ゼロの中小企業もあれば、企業規模も高卒者も大卒者も関係なく、就職後3年以内の離職率は3割を超えていたりもします。一方、65歳までの定年延長や70歳までの就業機会確保の努力義務などの永く働くことができる仕組みができても、高齢になればなったで健康問題や家族の事情で働きたくても働けない、あえて働かないことを選ぶ人もたくさんいます。 特に、中小企業では、人手確保のために定年延長に頼るだけでなく、受け皿となる人材を増やし、後進への技術伝承や事業承継を進めながら、会社の若返りを進めなくてはなりません。経営者自身の若返りは、後継者さえいれば自らの決断ですぐ実現しますが、会社の若返りはそうはいきません。 ついては・・・
終身雇用や年功序列、新卒一括採用といった言葉は死語となり、桜と入社式は無縁のものになっている・・・、そう遠くない未来かと思い浮かべながら、『年表』と『ピラミッド』から打つべき手を考え、春、次へと動く季節です。 以 上 |
| <真> 2024年4月 |
今を生きるVol.57 |
|
一年のうちで最も希望に溢れ平和を願う心で世の中が満たされている日、神に願ったところで空しいことと思うか、神に願ったからこそ救われたと思うか。いずれにせよ、天に人間の暦は関係なく、何事も人間の思い通りにはいかないことを思い知らされました。 震災やコロナを経験して、人間の力ではどうにもならないことがあるとわかっていたはずなのに、すぐに忘れて、すぐ他人事になって、『明日も元気。来年もきっと。なんとかなる。』と考えてしまうのが“ニンゲン”という生き物の悲しいところでもあります。 平穏で何気ない日常が続くことこそが幸せや平和であるということを“ニンゲン”に気づかせるため、天は、新年早々に警鐘を鳴らしたのかもしれません。なんでもない日々が続くことこそがありがたいこと、でも、当たり前のことが当たり前でなくなる時はいつ来てもおかしくはない、のだと。 でも、ニンゲンは、強くて賢い生き物でもあります。今、先が見えなくて不安な方も一日一日を大切に生きてください。寒さ、不自由さ、辛さ、悲しみをなんとか乗り越えてください。目の前の現実はどんなに辛くても悲しくても、朝は必ず来ます、空は晴れ、冬が終われば春は必ずやってきます。 今を生きるものには、ニンゲンという生き物として有する経験と知恵と行動でもって、生命をつなぎ、社会を維持する使命があります。 2024年、一人でも多くの人が笑顔で前を向いて進める一年になりますように。 以 上 |
| <真> 2024年1月 |