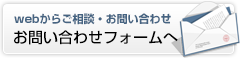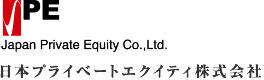コラム “志・継・夢・承”
|
2024年 |
-
2024年1月 Vol.57今を生きる
今を生きるVol.57 |
|
一年のうちで最も希望に溢れ平和を願う心で世の中が満たされている日、神に願ったところで空しいことと思うか、神に願ったからこそ救われたと思うか。いずれにせよ、天に人間の暦は関係なく、何事も人間の思い通りにはいかないことを思い知らされました。 震災やコロナを経験して、人間の力ではどうにもならないことがあるとわかっていたはずなのに、すぐに忘れて、すぐ他人事になって、『明日も元気。来年もきっと。なんとかなる。』と考えてしまうのが“ニンゲン”という生き物の悲しいところでもあります。 平穏で何気ない日常が続くことこそが幸せや平和であるということを“ニンゲン”に気づかせるため、天は、新年早々に警鐘を鳴らしたのかもしれません。なんでもない日々が続くことこそがありがたいこと、でも、当たり前のことが当たり前でなくなる時はいつ来てもおかしくはない、のだと。 でも、ニンゲンは、強くて賢い生き物でもあります。今、先が見えなくて不安な方も一日一日を大切に生きてください。寒さ、不自由さ、辛さ、悲しみをなんとか乗り越えてください。目の前の現実はどんなに辛くても悲しくても、朝は必ず来ます、空は晴れ、冬が終われば春は必ずやってきます。 今を生きるものには、ニンゲンという生き物として有する経験と知恵と行動でもって、生命をつなぎ、社会を維持する使命があります。 2024年、一人でも多くの人が笑顔で前を向いて進める一年になりますように。 以 上 |
| <真> 2024年1月 |